「就活に役立つ資格がほしい」
「不動産業界に興味はあるけど、何をすればいいかわからない」
そんな大学生に向けて、宅建取得のメリットを徹底的に解説します。
この記事では、
- 宅建取得が就活で強い理由
- 大学生が今こそ狙うべき理由
- 宅建で有利になる業界
- 合格のための勉強法
を、不動産業界歴15年の現役宅建士がリアルな経験をもとに紹介します!
Contents
宅建取得が就活に強い3つの理由
① 難易度が手頃なのに独占業務がある
宅建士だけに許された重要事項説明・契約書への記名押印といった独占業務。
それでいて難易度は行政書士や社労士よりも手頃。
国家資格なのに、最強コスパです。
② 不動産会社は「宅建士設置義務」がある
営業所に5人に1人以上宅建士を置くことが法律で義務付けられています。
企業はいつも宅建士を求めているため、就活で圧倒的アドバンテージになります。
③ 資格手当で初任給から差がつく
宅建手当は月5,000円〜30,000円が相場。
月3万円なら年間36万円、10年で360万円の差!
収入面でも早くから差がつきます。
宅建取得で就活無双できる理由をさらに深掘り!
就活面接で確実にアピールできる
資格なし学生と宅建取得済み学生が並べば、間違いなく宅建持ちが選ばれやすい。
「努力できる人」「業界知識がある人」と評価されます。
宅建取得で給料が高くなる
宅建資格手当だけでなく、昇進・評価でも有利になる可能性あり!
大学生は勉強時間に恵まれている
社会人受験生は時間が取れず苦戦しています。
大学生なら勉強時間を武器にできるので圧倒的に有利!
宅建で有利になる業界3選
不動産業界
独占業務あり+設置義務あり。宅建士は常に求められている業界です。
求人でも「宅建必須」「宅建歓迎」がズラリ。
建設業界
建設会社が不動産販売も行っているケース多数。
ハウスメーカー・ゼネコンでも宅建士が活躍しています。
金融業界
銀行・信託銀行でも不動産担保ローンや不動産信託業務に宅建知識が必要。
特に信託銀行では宅建士が高評価!
宅建試験の基本情報【2024年版】
- 試験日:10月第3週日曜日
- 形式:四肢択一マークシート
- 合格率:約15〜17%
- 勉強時間:300〜500時間目安
- 受験資格:年齢・学歴不問
小学4年生の合格者もいるので、本気なら誰でもチャンスあり!
宅建合格に向けたおすすめ勉強法
結論:通信講座が最強!
| スタイル | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 独学 | 費用が安い/自由度高い | 効率が悪い/自己管理が大変 |
| 通学 | 質問できる/モチベ維持しやすい | 費用高い/通学負担 |
| 通信講座 | 効率的/費用も比較的抑えられる | モチベーション管理が必要 |
私自身、独学で苦労した経験から通信講座を推します。
特にアガルート宅建講座は初心者でも安心です!
まとめ:今すぐ宅建勉強を始めよう!
宅建取得は、
- 就活で無双できる
- 同期より給料が高い
- 一生役立つ知識になる
未来を変えたいなら、まずは今日からテキストを開くこと。
あなたの努力は、きっと未来のあなたを救います!
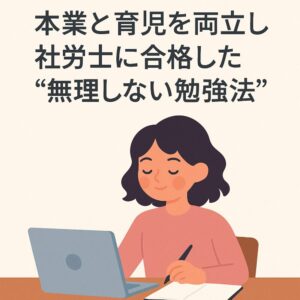
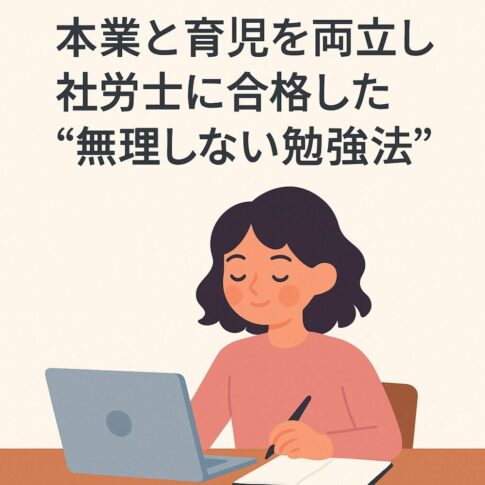

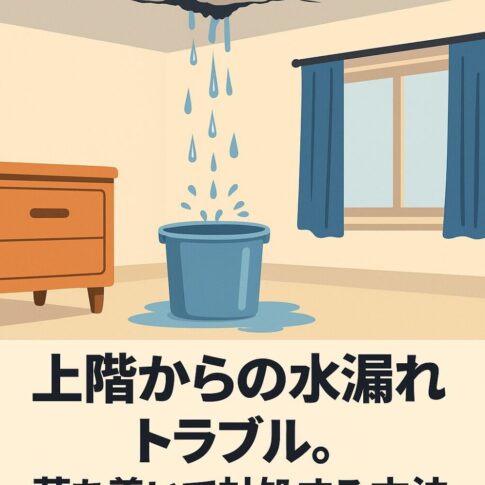
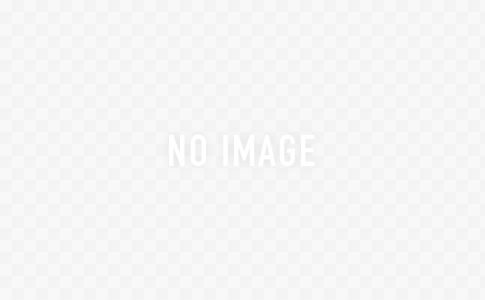
コメントを残す